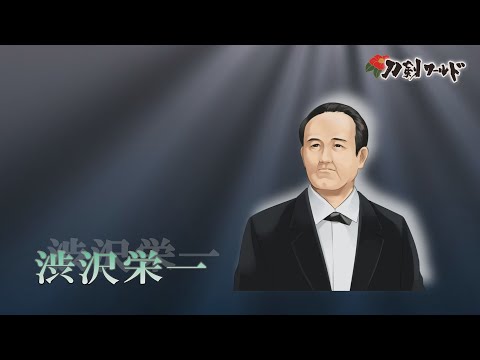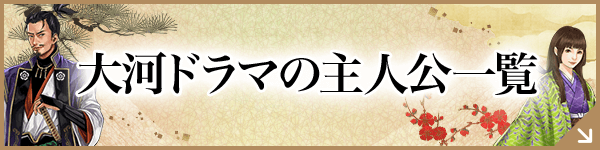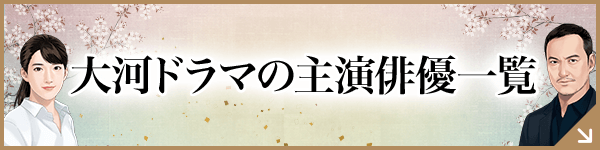NHK大河ドラマ ~青天を衝け~ - ホームメイト
- 小
- 中
- 大
NHK大河ドラマ ~青天を衝け~の基本情報
| 脚本 | 大森美香 |
|---|---|
| 音楽 | 佐藤直紀 |
| 題字 | 杉本博司 |
| 放送日 | 初回:2021年2月14日 最終回:2021年12月26日 |
| 放送時間 | 総合テレビ:毎週日曜 20時 NHK BS4K:毎週日曜 18時 NHK BSプレミアム:毎週日曜 18時 |
| 出演・キャスト | 吉沢亮 高良健吾 橋本愛 草彅剛 和久井映見 木村佳乃 竹中直人 堤真一 小林薫 他 |
| 語り | 守本奈実 |
| ブルーレイ&DVD発売日 | 2022年3月25日発売 |
タイトル「青天を衝け」の意味とあらすじ
日本の「新紙幣の顔」に選ばれた、「渋沢栄一」(しぶさわえいいち)。注目が高まるなか、2019年(令和元年)9月に制作発表されたのが、渋沢栄一を主人公としたNHK大河ドラマ「青天を衝け」です。
タイトルの青天を衝けは、渋沢栄一の名言である「勢衝青天攘臂躋 気穿白雲唾手征」(青空をつきさす勢いで肘をまくって登り、白雲をつきぬける気力で手に唾して進む)から取られたもの。

藍玉
これは、若き渋沢栄一が家業の「製藍業」(藍植物を収穫して藍染めの原料を製造・販売する業者)を手伝っていた頃、藍玉(あいだま:加工され玉状になった藍染めの原料。このもととなる物を染[すくも]と呼ぶ)を売るために信州へ旅をして、険しい渓谷の内山峡(うちやまきょう:現在の長野県佐久市)を登った際に詠んだ漢詩の一節だと言われています。
このタイトルからも分かるように、青天を衝けは、渋沢栄一の故郷である武蔵国榛沢郡血洗島村(むさしのくにはんざわぐんちあらいじまむら:現在の埼玉県深谷市)を舞台に、若き渋沢栄一を描く「血洗島・青春編」から始まるのです。
そののち、物語は幕末の動乱のなかで身分制度への怒りを覚えた渋沢栄一が、「尊王攘夷」(そんのうじょうい:天皇を尊び政治の中心とする尊王と外国を追い払う攘夷が結びついた思想)に傾倒していく青年期へ。幕臣となってパリへ渡った転換期、新政府へ入り、日本の改革を推し進めた成人期までの激動の物語を濃密に描いていきます。
青天を衝けは、渋沢栄一のルーツや人生を辿りながら、日本の変革期を体感していく物語となっているのです。
毎週放送回のあらすじ
2021年(令和3年)から放送のNHK大河ドラマ第60作「青天を衝け」(せいてんをつけ)は、幕末から明治時代を駆け抜けた「渋沢栄一」(しぶさわえいいち)の生涯が描かれています。また「青天を衝け」はNHK大河ドラマとしては珍しく、日本資本主義の礎を築いた渋沢栄一が主人公の近代史で、ドラマが放送される前から注目を集めていました。ここでは、渋沢栄一を中心に激動の時代を舞台とした「青天を衝け」について、毎週放送後にあらすじとトピックをご紹介します。
第1回 栄一、目覚める(2021年2月14日放送)
武蔵国血洗島(現在の埼玉県深谷市)で誕生した渋沢栄一(子役:小林優仁)は、おしゃべりかつ強情っぱりな性格で、大人達を困らせていました。4歳のときに母・渋沢ゑい(和久井映見)から「あなたが嬉しいだけでなく、みんなが嬉しいのが一番」と教えられ、6歳からは父・渋沢市郎右衛門(小林薫)に読み書きを教えてもらうようになります。また、罪人として捕まえられている砲術家・高島秋帆(玉木宏)と遭遇。「このままでは日本は終わる」と言われ、自分が日本を守ると宣言するのでした。
一方、江戸では水戸藩主・徳川斉昭(竹中直人)の息子である七郎麻呂(子役:笠松基生)を御三卿である一橋家に迎える話が進みます。一橋家養子となった七郎麻呂は、将軍・徳川家慶(吉幾三)から「慶」を賜り、名を「慶喜」と改めました。
今週のトピック
第1話は、渋沢栄一(吉沢亮)・渋沢喜作(高良健吾)が徳川慶喜(草彅剛)に自分を取り立てるよう願い出るシーンから始まりました。このあとから子ども時代にさかのぼったので、最初のシーンに至る過程が楽しみです。
また、高島秋帆との場面も見どころでした。「このままではこの国は終わる。誰かが守らなくてはな。この国は」と語る高島秋帆に、「俺が守ってやんべぇ、この国を」と宣言する渋沢栄一。渋沢栄一がここからどのように成長していくのか、目が離せません。
第2回 栄一、踊る(2021年2月21日放送)
渋沢栄一(子役:小林優仁)は9歳になり、父・渋沢市郎右衛門(小林薫)から藍の商売について習い始めました。そんなある日、岡部藩代官が渋沢家を訪れます。代官は100人の人手と御用金2,000両を要求。この要求が影響し、村の祭りは延期になってしまいました。忙しさに明け暮れる大人達を元気付けるため、渋沢栄一はいとこの渋沢喜作(子役:石澤柊斗)らと、祭りで行うはずだった獅子舞を披露します。
一方、一橋家に入った徳川慶喜(子役:笠松基生)は、将軍・徳川家慶(吉幾三)にかわいがられていました。隠居の身であった徳川斉昭は、息子である徳川慶喜をきっかけにして、政界に返り咲こうとします。
それから数年が経ち、アメリカからペリー(モーリー・ロバートソン)が日本に来ることになりました。
今週のトピック
第3回 栄一、仕事はじめ(2021年2月28日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)は父・渋沢市郎右衛門(小林薫)に連れられて、初めて江戸に赴きます。そして武力ではなく商いで成り立っている江戸の街を見て、胸を高鳴らせるのでした。なお、この年、藍畑が虫の被害に遭い、渋沢市郎右衛門は藍の葉の買い付けに向かいます。渋沢栄一も協力しようと思い、目利きを発揮して藍葉を買い付けることに成功しました。
一方、4隻の黒船が来航し、江戸のみならず血洗島も大騒ぎ。さらにこの頃、徳川家慶(吉幾三)が亡くなりました。幕府によって隠居の処分を解かれた徳川斉昭(竹中直人)は、息子・徳川慶喜(草彅剛)に将軍になるよう言いますが、徳川慶喜は却下。また、徳川慶喜を支える側近として、平岡円四郎(堤真一)に白羽の矢が立ちます。
今週のトピック
第4回 栄一、怒る(2021年3月7日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)は、「日本を外国から守らなければならない」と考える従兄・尾高惇忠(田辺誠一)と語り合う日々を送っていました。仕事にも励み、宴会の際に良い藍を作った人物から上座に座ってもらうことを考案。百姓が互いに高め合うことで藍作りを盛り上げようとします。
なお、幕府では、ペリー(モーリー・ロバートソン)の再来航が迫り混乱。井伊直弼(岸谷五朗)らは開国を迫りますが、攘夷を推進する徳川斉昭(竹中直人)は許しません。老中・阿部正弘(大谷亮平)は迷った末、日米和親条約を締結しました。一方で、平岡円四郎(堤真一)は、主君となった徳川慶喜(草彅剛)の人柄に惹かれます。
血洗島では、岡部藩代官が渋沢家に多額の御用金を要求。渋沢栄一は理不尽さに納得できないまま、御用金を届けに行くのでした。
今週のトピック
第5回 栄一、揺れる(2021年3月14日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)は従兄・尾高惇忠(田辺誠一)に1冊の本を渡されました。その本には清がイギリスに倒された顛末が記載されており、渋沢栄一は開国した日本を危惧し、攘夷の思いを強くします。そんなある日、渋沢栄一の姉・渋沢なか(村川絵梨)は、「縁談相手の家に憑き物がいる」という理由で伯父と伯母に縁談を反対されてしまいました。ふさぎこむ渋沢なかでしたが、伯母が連れてきた修験者らに対して渋沢栄一が反論し、追い返したことで元気になります。
一方、幕府の方針を受け入れられない徳川斉昭(竹中直人)は暴走。津波で転覆したロシア船乗組員達を皆殺しにしろとまで言う始末です。そんな徳川斉昭を側近・藤田東湖(渡辺いっけい)がなだめます。
そして1855年(安政2年)、大地震が発生。この地震により、藤田東湖は亡くなってしまいました。
今週のトピック
第6回 栄一、胸騒ぎ(2021年3月21日放送)
渋沢栄一は従兄の尾高長七郎(満島真之介)、渋沢喜作(高良健吾)とともに剣の稽古に励む日々を送っていました。ある日、尾高千代(橋本愛)から思いを告げられた渋沢栄一は、胸がぐるぐるするような感覚を覚えます。そんな矢先、道場破り・真田範之助(板橋駿谷)が道場に訪問。尾高長七郎が打ち負かします。
一方、徳川慶喜(草彅剛)は美賀君(川栄李奈)を正室に迎えますが、妻に関心がありません。しかし養祖母である徳信院(美村里江)とは仲が良く、美賀君は徳川慶喜と徳信院の仲を疑って騒動を起こします。また、徳川斉昭(竹中直人)は暴走気味になっており、息子の徳川慶喜と徳川慶篤(中島歩)は引退を勧めますが、却下されてしまうのでした。
今週のトピック
第7回 青天の栄一(2021年3月28日放送)
老中・阿部正弘(大谷亮平)が急死し、開国派の堀田正睦(佐戸井けん太)が後任を務めます。また、徳川慶喜(草彅剛)を将軍に推す声も高まっている一方で、将軍・徳川家定(渡辺大知)には井伊直弼(岸谷五朗)が近付いていきました。
なお、尾高千代(橋本愛)とぎくしゃくしていた渋沢栄一(吉沢亮)でしたが、渋沢喜作(高良健吾)が「千代を嫁にほしい」と言い出したことで動揺。2人は喧嘩してしまいます。そんな折、江戸に行った尾高長七郎(満島真之介)から手紙が届きました。渋沢栄一宛の手紙には、「お前と千代は思い合ってると思っていた」「お前はこのままでいいのか」とあります。その後、尾高惇忠(田辺誠一)と藍売りの旅に出た渋沢栄一は、山を歩きながら自分の思いに気付き、血洗島に帰ると尾高千代にその思いを伝えるのでした。
今週のトピック
第7回の渋沢栄一は、尾高千代との恋が見どころでした。渋沢喜作が尾高千代との結婚を言い出したことで動揺していた渋沢栄一ですが、自分の本当の気持ちに気付き、「お千代、俺はお前が欲しい」と告白。尾高千代・渋沢喜作との関係が今後どうなるのか気になるところです。
また、「私は青天を衝く勢いで 白雲を突き抜けるほどの勢いで進む」という漢詩が登場した、藍売り道中のシーンも印象的。壮大な景色の映像も圧巻でした。
第8回 栄一の祝言(2021年4月4日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)は尾高千代(橋本愛)に求婚します。そこにやって来たのは渋沢喜作(高良健吾)。尾高千代を巡って剣術で一戦交えます。勝利した渋沢喜作でしたが、尾高千代に「栄一の面倒を見てくれ」と頼みます。そして尾高惇忠(田辺誠一)に結婚の許可を得て、渋沢栄一・尾高千代は祝言を挙げ、夫婦となりました。
一方、江戸では将軍・徳川家定(渡辺大知)が井伊直弼(岸谷五朗)を大老に任命。またこの頃、天皇の許可を得ることなく、日米修好通商条約が結ばれました。徳川慶喜(草彅剛)は、井伊直弼が調印を書状のみで天皇に伝えたことを叱責。その後、病床に伏せていた徳川家定は井伊直弼に徳川斉昭(竹中直人)らを処分するよう伝えるのでした。
今週のトピック
第9回 栄一と桜田門外の変(2021年4月11日放送)
井伊直弼(岸谷五朗)によって処分を受けた徳川斉昭(竹中直人)や徳川慶喜(草彅剛)達。徳川斉昭は終身にわたる謹慎、徳川慶喜は隠居・謹慎を命じられ、無言の抵抗を続けていました。そんななか、桜田門外の変で井伊直弼が討たれ、徳川斉昭も急死。父親の死を知った徳川慶喜は嘆き悲しみます。
一方、江戸から帰ってきた尾高長七郎(満島真之介)の話を聞いた渋沢栄一(吉沢亮)は、尊王攘夷の考えに傾倒していました。また、「生まれつき身分があるこの世自体がおかしいのかもしれない」と、妻・渋沢千代(橋本愛)に話します。さらに、尾高長七郎に続いて渋沢喜作(高良健吾)も江戸に向かうことになり、渋沢栄一も「春の少しの間だけでいいから江戸に行かせてほしい」と父・渋沢市郎右衛門(小林薫)に頼むのでした。
今週のトピック
第10回 栄一、志士になる(2021年4月18日放送)
桜田門外の変で暗殺された井伊直弼(岸谷五朗)に代わり、老中・安藤信正(岩瀬亮)は和宮(深川麻衣)の将軍・徳川家茂(磯村勇斗)への降嫁を進めていました。和宮は孝明天皇(尾上右近)の妹にあたる人物。この降嫁には幕府の権威を回復する目論見があり、尊王攘夷派の志士らを刺激します。
一方、渋沢栄一(吉沢亮)は、父・渋沢市郎右衛門(小林薫)に許可を得て江戸に訪れました。そして渋沢喜作(高良健吾)に連れられて思誠塾に向かい、尊王攘夷を唱える大橋訥庵(山崎銀之丞)に会います。また、血洗島に戻った渋沢栄一のもとに尾高長七郎(満島真之介)が訪問。「安藤信正を暗殺して切腹する」と話す尾高長七郎を、尾高惇忠(田辺誠一)と渋沢栄一は制止します。
尾高長七郎は尾高惇忠にしたがって身を隠していたため捕まりませんでしたが、暗殺に参加した者達は返り討ちにされてしまうのでした。
今週のトピック
第11回 横濱焼き討ち計画(2021年4月25日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)は江戸に向かう尾高長七郎(満島真之介)に追い付き、安藤信正(岩瀬亮)の暗殺が失敗したこと、暗殺にかかわった者を幕府が探していることを伝えます。説得された尾高長七郎は、江戸行きを断念しました。
それから1ヵ月後、渋沢栄一と渋沢千代(橋本愛)の間に第一子・市太郎が誕生。しかし、市太郎は「はしか」で亡くなってしまいます。なお、尾高惇忠(田辺誠一)は、横浜外国人居留地の焼き討ちを計画。渋沢栄一は渋沢喜作(高良健吾)と江戸で武器を集めます。また、父・渋沢市郎右衛門(小林薫)に勘当を申し出るのでした。
一方、謹慎を解かれた徳川慶喜(草彅剛)は、将軍・徳川家茂(磯村勇斗)の後見職に就任。島津久光(池田成志)らから攘夷の決行を迫られますが、異を唱えます。
今週のトピック
第12回 栄一の旅立ち(2021年5月2日放送)
江戸を訪れた渋沢栄一(吉沢亮)と渋沢喜作(高良健吾)は、平岡円四郎(堤真一)に出会いました。話を聞いた平岡円四郎は、自分に仕えて武士になった方が良いと勧めますが、2人は断りました。
尾高惇忠(田辺誠一)が計画した外国人焼き討ちの日が迫ってきた頃、尾高長七郎(満島真之介)が血洗島に現れます。尾高長七郎は攘夷の現状を話し、「天皇は幕府を選んだ」「お前達の命を犬死で終わらせたくないんだ」と、涙ながらに計画の中止を訴え、計画は断念されることに。尾高長七郎の思いに自分が間違っていたことを気付かされた渋沢栄一は、初めて娘・うたを抱きます。そして父・渋沢市郎右衛門(小林薫)にこれまでの経緯を話した上で、渋沢喜作とともに、村を出て京に向かうのでした。
今週のトピック
第13回 栄一、京の都へ(2021年5月9日放送)
京都へ向かおうとする渋沢栄一(吉沢亮)と渋沢喜作(高良健吾)は、力を借りようと平岡円四郎(堤真一)邸を訪れました。平岡円四郎は不在でしたが、その妻・平岡やす(木村佳乃)から平岡家の家臣であることを示す証文を受け取り、京都にたどり着きます。
なお、京都では朝廷が参与会議を開いており、徳川慶喜(草彅剛)や松平春嶽(要潤)、島津久光(池田成志)、松平容保(小日向星一)らが参加していました。松平春嶽は「一度すべて捨てて、新しい世を作ろう」と話し、徳川慶喜は腹を立てます。
一方、渋沢栄一は横浜焼き討ちについて記載した手紙を血洗島に送りました。尾高惇忠は、尾高長七郎(満島真之介)を京都に向かわせますが、尾高長七郎は道中で人を斬り、捕まってしまいます。手紙も見付かってしまい、渋沢栄一・渋沢喜作は幕府から目を付けられ追い詰められてしまうのです。
今週のトピック
第14回 栄一と運命の主君(2021年5月16日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)・渋沢喜作(高良健吾)は、平岡円四郎(堤真一)に「一橋家の家来になれ」と言われます。2人は話し合った上で、徳川慶喜(草彅剛)に自分の意見を述べることが条件だと伝えました。平岡円四郎は、渋沢栄一らと徳川慶喜を対面させることに成功。馬に乗る徳川慶喜に、渋沢栄一は自分の考えを伝えます。さらにその数日後、徳川慶喜の屋敷でも意見を述べ、2人は一橋家に仕えることになりました。
この頃、徳川慶喜は、天皇から厚く信頼されている中川宮(奥田洋平)が薩摩藩に取り込まれていることに気付きます。そして中川宮を問い詰め、薩摩勢である島津久光(池田成志)らを批判。「政権を返上させることなく、徳川を守る」という決意をするのでした。
今週のトピック
第15回 篤太夫、薩摩潜入(2021年5月23日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)・渋沢喜作(高良健吾)が一橋家家臣となってから1ヵ月が経ち、2人は初俸禄をもらうとともに、平岡円四郎(堤真一)からそれぞれ「篤太夫」「成一郎」という名を授かります。そして渋沢栄一は薩摩藩の折田要蔵(徳井優)を探る隠密調査を命じられました。隠密調査中、西郷隆盛(博多華丸)と出会い、この先の世について話を交わします。渋沢栄一は西郷隆盛から「先の時代が読める優秀な人間ほど非業の死を遂げてしまう」と言われ、平岡円四郎のことを不安に思うのでした。また、この隠密調査で薩摩藩が折田要蔵を通して朝廷に働きかけていることが分かった平岡円四郎は、徳川慶喜(草彅剛)に報告し、先手を打ち始めます。
一方、水戸藩では藤田東湖(渡辺いっけい)の息子である藤田小四郎(藤原季節)が攘夷のため、天狗党を挙兵させました。
今週のトピック
第16回 恩人暗殺(2021年5月30日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)・渋沢喜作(高良健吾)は、一橋家家臣と兵を集めるために関東に向かいました。2人は手広く人材を探し、そしてかつての同志だった真田範之助(板谷駿谷)を訪問。「国をより良くするために一緒に一橋家で働かないか」と提案しますが、一蹴されてしまいます。
血洗島では、尾高惇忠(田辺誠一)と尾高平九郎(岡田健史)が天狗党に関する騒動に携わったとして連行されてしまいました。一方、京都では、新選組が尊王攘夷の志士らを取り締まるため、池田屋を襲撃。そこにいた志士らは殺害されました。水戸藩士らは黒幕が徳川慶喜、もしくは平岡円四郎でないかと疑います。そして平岡円四郎は討たれ、亡骸を見た徳川慶喜は嘆き悲しむのでした。
今週のトピック
第17回 篤太夫、涙の帰京(2021年6月6日放送)
一橋家のために集めた人々を連れ、渋沢栄一(吉沢亮)と渋沢喜作(高良健吾)は江戸に向かいました。そこで2人は恩人・平岡円四郎(堤真一)が殺されたことを知り、愕然とします。
また、京都では徳川慶喜(草彅剛)が指揮を執り、天皇を奪還すべく挙兵した長州藩と戦っていました。世に言う「禁門の変」です。西郷隆盛(博多華丸)率いる薩摩藩の兵らの加勢もあって、幕府側の勝利で終わりました。
一方、集めた兵とともに京に移動する渋沢栄一らは、その道中で、かつて理不尽に渋沢栄一を罵った岡部藩代官・利根吉春(酒向芳)と再会します。「渋沢栄一・渋沢喜作を岡部藩に戻せ」と言う利根吉春ですが、一橋家家臣・猪飼勝三郎(遠山俊也)は拒否。利根吉春は道を開けざるを得ません。
なお、水戸では徳川慶喜を頼り、武田耕雲斎(津田寛治)と藤田小四郎(藤原季節)ら天狗党が京に向かっていました。
今週のトピック
第18回 一橋の懐(2021年6月13日放送)
天狗党を討つために一橋家は挙兵し、渋沢栄一(吉沢亮)も集めた兵と出兵します。しかし、徳川慶喜(草彅剛)の手紙を見た天狗党の武田耕雲斎(津田寛治)は投降を決意。渋沢栄一の天狗党討伐は戦うことなく終わりました。徳川慶喜は天狗党の処分を引き受けようとしますが、幕府の田沼意尊(田中美央)は天狗党の者達の首をはねてしまいます。また、一橋家を強化したいと思った渋沢栄一は、兵の招集を徳川慶喜に意見。「軍制御用掛 歩兵取立御用掛」に任命され、備中国(現在の岡山県西部)に向かいます。最初は難航したものの、結果として多くの人を集めることに成功しました。徳川慶喜より褒美をもらう渋沢栄一でしたが、さらに一橋家を強く、そして懐を豊かにすることを提案します。
今週のトピック
第19回 勘定組頭 渋沢篤太夫(2021年6月20日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)は一橋家の懐を豊かにするため、動き始めました。米を高値で売るとともに、火薬の原料である硝石の製造所も作っていきます。さらに、木綿の売り買いの流れを良くするため、銀札作りにも着手。百姓達からも信用を得ます。結果として、渋沢栄一は「勘定組頭」の職を任じられるのでした。
一方、幕府はイギリスが兵庫の開港を迫ってきたことで混乱。勅許(ちょっきょ:天皇の許可)を巡る攻防が繰り広げられます。また、江戸幕府は2度目の長州征伐をスタートしました。長州藩はひそかに薩摩藩と同盟(薩長同盟)を結んでおり、幕府は大苦戦。そんななか、指揮を執っていた将軍・徳川家茂(磯村勇斗)が胸を押さえて倒れこんでしまいました。
今週のトピック
第20回 篤太夫、青天の霹靂(2021年6月27日放送)
徳川家茂(磯村勇斗)が亡くなりました。次の将軍は徳川慶喜(草彅剛)になるかもしれないと聞いた渋沢栄一は、「今将軍になっても、非難を一身に受けることになる」と、将軍家を継がないように徳川慶喜本人に進言します。
一方、薩摩藩の大久保一蔵(石丸幹二)は、公家・岩倉具視(山内圭哉)と王政復古を画策。「薩摩藩と長州藩は幕府を捨てて天皇中心の世にする」と言う大久保一蔵に、岩倉具視は感心し、倒幕派へと傾いていたのです。
また、徳川慶喜が徳川宗家を継いだことにより幕臣となった渋沢栄一は、失意の日々を過ごしていました。そんななか、ある謀反人の捕縛を命令されます。渋沢栄一の警護を任じられたのは、新選組副長・土方歳三(町田啓太)でした。
今週のトピック
第21回 篤太夫、遠き道へ(2021年7月4日放送)
パリ万国博覧会に徳川慶喜(草彅剛)の弟・徳川昭武(板垣李光人)が参加することになりました。また、徳川昭武は展覧会後もパリに留まり、洋学を学ぶ予定となっています。この随行を打診された渋沢栄一(吉沢亮)は、その場で「行かせてほしい」と即答しました。一方、徳川慶喜は第15代征夷大将軍に就任。渋沢栄一を呼び出して、「弟を頼む」と話すのでした。
その後、徳川昭武一行は横浜に到着。渋沢栄一は幕府の勘定奉行である小栗忠順(武田真治)に対面します。そこでフランス行きには、600万ドルを借り入れる目的があることを知らされました。さらに、渋沢喜作(高良健吾)と再会。牢に囚われている尾高長七郎(満島真之介)とも面会します。
そして1867年(慶応3年)1月11日、横浜港から船に乗り込んだ渋沢栄一は、フランスへと旅立つのでした。
今週のトピック
第22回 篤太夫、パリへ(2021年7月11日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)ら一行はパリに到着し、万国博覧会の見学に出かけました。そこで目にした蒸気機関車やエレベーターなどに、渋沢栄一は大感動です。しかし、日本の展示ブースに行くと、日本と薩摩が別の国であるかのようになっていました。幕府一行は抗議しますが、薩摩に付いていたモンブラン伯爵(ジェフリー・ロウ)によってうまく丸め込まれます。そして翌日の新聞には「日本は連邦国」と記載されてしまい、幕府と薩摩が同格の政府であると噂が立ってしまうのです。そんななか、徳川昭武(稲垣李光人)はナポレオン3世の謁見式に出席。徳川慶喜(草彅剛)からの国書を堂々と読み上げ、名代の役目を果たします。
一方日本では、徳川慶喜が外国の支援を得て改革を進めていました。
今週のトピック
第23回 篤太夫と最後の将軍(2021年7月18日放送)
「日本は連邦国」とフランスの新聞に記載されたことで、徳川慶喜(草彅剛)が一大名に過ぎないことになり、600万ドルの借り入れができなくなってしまいます。しかし渋沢栄一(吉沢亮)が資金をなんとか調達し、徳川昭武(板垣李光人)は留学を続けていました。一行は教師に任命されたヴィレットにしたがって、髷を落とし洋装して、刀も外します。また、渋沢栄一は銀行オーナーが陸軍大佐と親しくしていたり、王が自ら特産品を売り込んでいたりといった姿を見て、外国では誰もが身分関係なく国のために励んでいると感じていました。
一方、日本では西郷隆盛(博多華丸)が兵を招集。フランスから借金もできておらず、軍の準備もできていない今、薩摩と戦っても幕府の負けは目に見えています。そこで徳川慶喜は大政奉還を宣言。倒幕を狙っていた薩摩と岩倉具視(山内圭哉)の目論見も無に帰します。
今週のトピック
第24回 パリの御一新(2021年8月15日放送)
幕府から使節団のもとに書状が届きました。書状には大政奉還がなされ、この先は薩摩藩らと政治を行っていくということが綴られています。一同は混乱しますが、渋沢栄一(吉沢亮)はその事実を受け止めていました。そして徳川昭武(板垣李光人)が外国で学び続けられるよう、さらなる倹約策を考えます。そんななか、渋沢栄一はエラール(グレッグ・デール)に証券会社に連れて行かれ、国債や社債について教えてもらいました。
また、使節団は横浜からの新聞や幕府からの書状で、幕府と朝廷が対立したこと、戦で幕府軍が敗走していることなどを知らされます。新政府から徳川昭武に対して帰国を要請する手紙も届き、一行は日本に帰ることになりました。
今週のトピック
第25回 篤太夫、帰国する(2021年8月22日放送)
1868年(明治元年)11月、渋沢栄一(吉沢亮)はフランスから帰国。先に帰国していた杉浦愛蔵(志尊淳)らと再会し、幕府が薩長に負けた経緯、徳川慶喜(草彅剛)が謹慎していること、江戸城が薩長に明け渡されたことなどを教えてもらいました。さらに、川村恵十郎(波岡一喜)と須永虎之助(萩原護)からは、彰義隊として新政府軍と戦っていた渋沢喜作(高良健吾)と尾高惇忠(田辺誠一)、渋沢平九郎(岡田健史)のことを聞きます。彰義隊は分裂して、渋沢喜作らは新たに振武軍と名乗るものの敗走。渋沢平九郎は死に、渋沢喜作は現在箱館で戦っていると知らされます。
また、渋沢栄一は水戸藩邸の徳川昭武(板垣李光人)を訪問。徳川慶喜宛の手紙を受け取ります。そして一度、血洗島に戻ることにしました。
今週のトピック
ついに元号が慶応から明治に変わり、江戸が東京と呼ばれるようになりました。日本で起きた様々な出来事を知らされた渋沢栄一ですが、特に渋沢平九郎の壮絶な最期を知り、絶句するシーンはあまりにも痛ましくて印象的。それでも「新しい世のためにできることはあるはずだ」と動く渋沢栄一の姿に胸を打たれました。
一方、洋装と白いハチマキという姿で新政府軍と激闘する土方歳三(町田啓太)の戦いぶりは圧巻です。
第26回 篤太夫、再会する(2021年9月12日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)は6年ぶりに帰郷。妻の渋沢千代(橋本愛)や父・渋沢市郎右衛門(小林薫)、母・渋沢ゑい(和久井映見)らと再会しました。また、養子にした渋沢平九郎(岡田健史)の死に責任を感じていた渋沢栄一は尾高家に謝罪に行こうとしますが、伯父・渋沢宗助(平泉成)から尾高長七郎(満島真之介)の死を知らされます。その後、尾高家で尾高惇忠(田辺誠一)と再会。生き残ってしまったことを悔いる尾高惇忠に対して、渋沢栄一は「今までの恥を胸に刻んで、生きている限り前に進みたい」と話しました。
その後、渋沢栄一は徳川昭武(板垣李光人)から預かっている手紙を届けるために、徳川慶喜(草彅剛)がいる駿府(現在の静岡県静岡市)に向かいます。徳川慶喜と謁見がかない、徳川昭武のフランスでの様子などを伝えました。
今週のトピック
第27回 篤太夫、駿府で励む(2021年9月19日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)は駿府藩の勘定組頭を命じられますが、断って水戸の徳川昭武(板垣李光人)に徳川慶喜(草彅剛)の手紙を届けようとします。しかし、この命は徳川慶喜(草彅剛)の配慮でした。水戸は内紛が続いていて、渋沢栄一が巻き込まれる可能性があるためです。徳川慶喜の配慮を知った渋沢栄一は、勘定組頭は断ったものの、駿府に残ることを決意します。そして借金から駿府藩を救うため、パリでの経験を活かし、銀行と商社をかねた「商法会所」を設立しました。
一方、箱館では、土方歳三(町田啓太)・渋沢喜作(高良健吾)ら旧幕府軍が新政府軍と戦闘。旧幕府軍は劣勢となっており、土方歳三は渋沢喜作を逃がします。そして自らは戦死していくのでした。
今週のトピック
第28回 篤太夫と八百万の神(2021年9月26日放送)
新政府から出仕を求められた渋沢栄一(吉沢亮)は、直接断ろうと東京を訪れました。大隈重信(大倉孝二)のもとに行って辞任を申し出ますが、大隈重信に「新しい世を作りたいと思ったことはないか」と言われ、胸が高鳴ります。
一方、戊辰戦争が終わり、徳川慶喜(草彅剛)はようやく謹慎を解かれました。渋沢栄一は徳川慶喜のもとを訪れ、東京でのことを話します。そして徳川慶喜は「この先は日本のために尽くせ」と最後の命を下すのです。「篤太夫」の名を返上した渋沢栄一は、徳川家への思いを胸に、明治新政府で働くことを決意しました。
渋沢栄一は明治政府に出仕し、首脳陣が集まる会議に参加。その場に大隈重信がいたことから自身が働く大蔵省であると勘違いし、岩倉具視(山内圭哉)ら政府首脳陣の前で現状を批判してしまうのでした。
今週のトピック
第29回 栄一、改正する(2021年10月3日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)は「改正掛」(かいせいがかり)を設置。改正掛は各省の垣根を超えた組織で、日本に必要な物事を広く考え、即実行することを目的としていました。そして静岡から呼んだ杉浦譲(志尊淳)や前島密(三浦誠己)らを加え、アイデアを出し合います。前島密が提案した「郵便制度」の確立に向けて話し合う面々でしたが、大隈重信(大倉孝二)が民部省から追い出され、改正掛は後ろ盾をなくしてしまいました。
そんななか、渋沢邸に尾高惇忠(田辺誠一)が訪れます。養蚕事業を任されていた渋沢栄一は、故郷で養蚕に励む尾高惇忠に新政府に来てほしいと誘いました。弟・渋沢平九郎(岡田健史)を新政府に殺されたことから、一度は断った尾高惇忠でしたが、最後には新政府を手助けすると決意。一方、徳川慶喜(草彅剛)は、渋沢栄一からの手紙を見て微笑むのでした。
今週のトピック
第30回 渋沢栄一の父(2021年10月10日放送)
新貨幣「円」の品質を確認するために大阪の造幣局に出張した渋沢栄一(吉沢亮)は、五代友厚(ディーン・フジオカ)と再会。パリ訪問の一件で暗躍していた五代友厚が借款を打ち切ったことなどを根に持っている渋沢栄一は、これまでの恨み言をぶつけます。
しかし、「民の利益のためにカンパニーを立ち上げて、日本の商業を魂から作り変えたい」という五代友厚の話に共感。一方、新政府の首脳会議では、制度改革の議論が行われますが、議論は一向にまとまりません。業を煮やした西郷隆盛(博多華丸)が突然、「まだ戦がたらん」と声を上げます。戦とは「廃藩置県を断行せよ」という意思表示のことだと西郷隆盛の意図を理解した井上馨(福士誠治)は、渋沢栄一や杉浦譲(志尊淳)らに極秘の任務を託すのでした。その準備期間はわずか4日。渋沢栄一らは寝る間も惜しんで、準備を整え、ついに1871年(明治4年)7月14日廃藩置県が行われます。
そして約1ヵ月経ったある冬の日のこと。東京に帰宅した渋沢栄一のもとに、父・渋沢市郎右衛門(小林薫)の危篤の知らせが届き、渋沢栄一は急いで血洗島へ戻るのでした。
今週のトピック
第31回 栄一、最後の変身(2021年10月17日放送)
新政府では大久保利通(石丸幹二)ら岩倉使節団が外遊をしていました。そのため、渋沢栄一(吉沢亮)をはじめ、三条実美(金井勇太)、西郷隆盛(博多華丸)、大隈重信(大倉孝二)、江藤新平(増田修一朗)、井上馨(福士誠治)らが新政府を仕切ることに。しかし、使節団がいない間に新規の改正ができないように、大久保利通は廃藩置県の業務しか許可しない「十二箇条の約定」を残していました。渋沢栄一は「廃藩置県の業務の一環ならできる」と考え、日本で初めてとなる銀行づくりに乗り出します。早速、豪商の小野組、三井組に協力を依頼するも難航。三井の番頭である三野村利左衛門(イッセー尾形)は、国との合同ではなく独自に銀行を作りたいと言い出し、渋沢栄一と対立します。
その頃、富岡製糸場の操業を始めたい尾高惇忠(田辺誠一)は、工女が集まらないことに悩んでいました。西洋式への誤解から、「生き血を取られる」という噂が立っていたのです。
尾高惇忠は娘の尾高ゆう(畑芽育)に伝習工女になってほしいと頼み込みます。そして尾高ゆうの決心をきっかけに、富岡製糸場には多くの工女が集まり、ようやく創業開始となったのでした。
今週のトピック
第32回 栄一、銀行を作る(2021年10月24日放送)
「官」ではなく「民」に入って実業の一線に立つことを決意した渋沢栄一(吉沢亮)は、井上馨(福士誠治)とともに大蔵省を辞職します。三井組の番頭・三野村利左衛門(イッセー尾形)の推薦を断り、いよいよ民間資本による「第一国立銀行」の総監役として新たな道を歩み始めることに。そして日本初となる第一国立銀行が開業した日に、渋沢栄一のもとに五代友厚(ディーン・フジオカ)が駆け付けてきます。五代友厚もまた大坂で鉱山のカンパニーを設立。そして五代友厚は、先に官を辞め、民に下った者として、渋沢栄一に「商いは化け物、魑魅魍魎(ちみもうりょう)が跋扈(ばっこ)している」と助言します。そんななか、三菱を率いる岩崎弥太郎(中村芝翫)は、大蔵卿に就任した大隈重信(大倉孝二)との関係を深め、海運業で急成長していました。その頃、体調を崩した渋沢栄一の母・渋沢ゑい(和久井映見)が東京の渋沢家で療養することになります。渋沢栄一は忙しいなかでもできるだけ、渋沢ゑいとの時間を作るのでした。
今週のトピック
第33回 論語と算盤(2021年10月31日放送)
第一国立銀行の大株主、小野組が放漫経営で危機に。もし小野組が破産すれば、無担保で多額の貸し付けをしていた第一国立銀行も、連鎖倒産の危機に陥ってしまいます。小野組や三井組に政府が無担保で貸し付けていた全額に対して大蔵省が「担保を出せ」と言い出したことに関して、渋沢栄一(吉沢亮)は大隈重信(大倉孝二)を非難しますが、埒が明きません。さらに三野村利左衛門(イッセー尾形)率いる三井組が、この機に乗じて第一国立銀行を乗っ取ろうと画策。渋沢栄一は第一国立銀行を守るため、大勝負にうって出ます。その頃、日本は機械や綿製品の輸入が増え、金貨や銀貨が海外へ流れるという、輸入超過にありました。
さらに横浜の外国商館が口裏を合わせ、主要の輸出品である蚕卵紙(さんらんし)を買い控えし、値崩れさせようと企んでいたのです。大久保利通(石丸幹二)は渋沢栄一を呼び出すと「国を助けるために味方になって欲しい」と頭を下げます。渋沢栄一はこの危機を乗り切るために、横浜の生糸職人を集め、ある作戦を頼むのでした。
今週のトピック
第33回では、第一国立銀行のピンチをはじめ、蚕卵紙の買い控えの危機を乗りきる渋沢栄一の手腕が輝いていました。一方、1877年(明治10年)は西南戦争が行われた年。西郷隆盛(博多華丸)はこの戦いで自害します。
また翌年1878年(明治11年)には大久保利通が不平士族に暗殺されるという衝撃的な事実も明らかになりました。再び新たな時代を迎える日本に対し、渋沢栄一がどのように活躍するのか気になります。
第34回 栄一と伝説の商人(2021年11月7日放送)
大隈重信(大倉孝二)による金融緩和で一時的に景気が良くなり、渋沢栄一(吉沢亮)のもとに銀行を作りたいという人達が集まるようになりました。一方、伊藤博文(山崎育三郎)らはイギリスのパークス(イアン・ムーア)に会い、20年前に結んだ不平等な「安政の五ヵ国条約」の改正を求めますが、議会のない日本では世論は把握できないと言われてしまいます。伊藤博文から「会議所を作って欲しい」という依頼を受けた渋沢栄一は、商人達が業種の垣根を越えて手を組むための組織「東京商法会議所」を作るのでした。
そんななか、渋沢栄一は三菱の岩崎弥太郎(中村芝翫)に宴席に誘われます。商業で国を豊かにしようという2人の考えは一致しますが、手法を巡って意見は対立。激論の末、会合は物別れに終わってしまいます。
その頃、元アメリカ大統領が来日することに。伊藤博文や岩倉具視(山内圭哉)らに依頼された渋沢栄一は、新しい日本の力を海外に示すため、大統領を盛大にもてなす準備を始めるのでした。
今週のトピック
第35回 栄一、もてなす(2021年11月14日放送)
アメリカ前大統領、ユリシーズ・グラント(フレデリック・ベノリエル)の来日が決まり、渋沢栄一(吉沢亮)や渋沢喜作(高良健吾)達が民間を代表して接待することになりました。渋沢栄一は、夫人同伴が当たり前の西洋流おもてなしを取り入れようと渋沢千代(橋本愛)や渋沢よし(成海璃子)に協力を願い出ます。そこへ井上武子(愛希れいか)や大隈綾子(朝倉あき)ら政財界の夫人も加わることに。渋沢千代や渋沢よしはヨーロッパに来航した経験のある井上武子から、握手やハグといった西洋式の挨拶を習います。
こうしてユリシーズ・グラント前大統領家族への歓迎は順調に進みますが、その後、ユリシーズ・グラント前大統領が「渋沢邸に行きたい」と言い出すことで、事態は急展開。悩む渋沢栄一に、渋沢千代は飛鳥山に建てたばかりの新居に招くことを提案します。
渋沢千代が中心となり、ユリシーズ・グラント前大統領を新居に迎える準備を始めるのでした。
今週のトピック
第36回 栄一と千代(2021年11月21日放送)
事業拡大を続ける三菱に対抗し、渋沢栄一(吉沢亮)は東京風帆船(とうきょうふうはんせん)会社を設立します。しかし、岩崎弥太郎(中村芝翫)は新聞を使い、渋沢栄一に関する偽の情報を広めることで、東京風帆船は開業前から苦しい状況に立たされてしまいます。さらに1881年(明治14年)には東京府によって、東京養育院の事業縮小を迫られることに。一方、北海道開拓使の工場が薩摩出身の五代友厚(ディーン・フジオカ)に不当な価格で払い下げられると報じられます。そのため、民衆は薩長出身の伊藤博文(山崎育三郎)や井上馨(福士誠治)らを悪者にし、彼らに反対した大隈重信(大倉孝二)を英雄視するまでになりました。大隈重信と対立していた伊藤博文はこれをきっかけに、大隈重信の罷免を決議。大隈重信を政府から追放したこの事件は「明治十四年の政変」と呼ばれます。
その頃、渋沢家では、渋沢栄一の長女である渋沢うた(小野莉奈)が穂積陳重(田村健太郎)と結婚。しかし幸せをかみしめるのも束の間、渋沢栄一の妻・渋沢千代(橋本愛)がコレラに感染し、倒れてしまいます。
今週のトピック
第37回 栄一、あがく(2021年11月28日放送)
渋沢栄一(吉沢亮)の最愛の妻・渋沢千代(橋本愛)が亡くなって3ヵ月が経過。政府の命により、再び岩崎弥太郎(中村芝翫)に対抗するため、海運会社「共同運輸会社」が設立されました。しかし、渋沢栄一は妻の死によりすっかり憔悴。見かねた知人らの勧めで、平岡やす(木村佳乃)のところにいる芸者見習の伊藤兼子(大島優子)と再婚することになります。
一方、共同運輸会社は三菱と熾烈な競争を繰り広げていました。両社ともが疲弊するなかで、突然、岩崎弥太郎が病死。そして五代友厚(ディーン・フジオカ)までもが病に倒れてしまいます。五代友厚は「これ以上の争いは不毛だ」と渋沢栄一を説得。岩崎弥太郎のあとを引き継いだ弟・岩崎弥之助(忍成修吾)との間を取り持とうとします。
時は流れ、1885年(明治18年)12月22日、日本に内閣制度が発足し、初代内閣総理大臣には伊藤博文(山崎育三郎)が任命。そして3年後には、伊藤博文が手がけた大日本帝国憲法が発布され、新たな国づくりが始まるのでした。
今週のトピック
第37回では、岩倉具視(山内圭哉)をはじめ、岩崎弥太郎や五代友厚らが死去という衝撃的な展開でした。なかでも「西の五代、東の渋沢」と呼ばれた五代友厚と渋沢栄一の会話は印象的です。日本のためにと切磋琢磨した2人の最後の言葉は胸に響きます。
また日本では初となる内閣制度が確立し、伊藤博文による大日本帝国憲法が発布。また新たな展開に今後も目が離せません。
第38回 栄一の嫡男(2021年12月5日放送)
1889年(明治22年)、渋沢栄一(吉沢亮)や旧幕臣達は、徳川家康の江戸入城300年の節目を祝う「東京開市三百年祭」を上野で開催。徳川昭武(板垣李光人)らと再会し、旧交を温めます。
その頃、渋沢家では渋沢栄一の息子・渋沢篤二(泉澤祐希)が、跡継ぎの重責に押し潰されそうになっていました。渋沢篤二は現実から逃れるかのようにある騒動を起こしてしまいます。渋沢栄一は、渋沢篤二を退学させ、謹慎処分として血洗島村に行くことを命じました。
一方、渋沢栄一の気がかりは、汚名を被ったまま静岡で暮らす徳川慶喜(草彅剛)のこと。渋沢栄一は徳川慶喜の功績を世に知らせようと、新聞社を経営する福地源一郎(犬飼貴丈)と、徳川慶喜の伝記を作ることを話し合っていました。
そんななか、日本は富国強兵を進め、1894年(明治27年)夏に日清戦争が勃発。この戦争で日本が勝利し、終結すると、渋沢栄一は徳川慶喜を東京へ呼び寄せるのでした。
今週のトピック
第39回 栄一と戦争(2021年12月12日放送)
1903年(明治36年)6月、渋沢栄一(吉沢亮)は、アメリカを訪れます。そして首都ワシントンのホワイトハウスでセオドア・ルーズベルト(ガイタノ・トタロ)大統領と会談。アメリカ大統領が日本の民間人と共同会見をすることは異例でもありました。しかし、この会談で渋沢栄一は、日本の軍事面のみが注目され、経済への評価が低いことを痛感します。やがて1904年(明治37年)日露戦争が勃発。井上馨(福士誠治)や陸軍参謀次長の児玉源太郎(萩野谷幸三)らに「財界にもロシアを討つべしと掲げてほしい」と頼まれた渋沢栄一は戦費に充てる公債購入を呼びかける演説をし、民間人に協力を要請。しかしその直後、病に倒れてしまいます。
そして病が悪化し、死を覚悟した渋沢栄一のもとへ徳川慶喜(草彅剛)が見舞いに訪れました。「生きてくれたら、何でも話す」と涙ながらに約束。徳川慶喜の見舞いもあってか、体調が回復した渋沢栄一は、徳川慶喜の功績を後世に伝えようと「徳川慶喜公伝」を作り始めるのでした。
今週のトピック
第40回 栄一、海を越えて(2021年12月19日放送)
1909年(明治42年)6月、渋沢栄一(吉沢亮)は第一国立銀行と銀行集会所以外の役員をすべて辞任し、実業界から引退します。そして、日本人移民排斥の動きを見せるアメリカに対し、日本人を理解してもらおうと妻・渋沢兼子(大島優子)達と渡米することを決意。日米親善に貢献するために、日本の実業家や学者、新聞記者などの視察団をまとめ、特別列車で全米60ヵ所の都市や施設を見学し、民間外交に力を注ぎます。
しかし旅の途中、明治政府のかなめとなって動いてきた伊藤博文(山崎育三郎)が中国のハルビン駅で暗殺。ショックを受けた渋沢栄一は伊藤博文の死に触れながら、商業会議所でスピーチを行い、多くのアメリカ人の胸を打ちます。
1911年(明治44年)、渋沢家では再び息子の渋沢篤二(泉澤祐希)が問題を起こしました。責任を感じた渋沢栄一は、渋沢篤二を廃嫡(はいちゃく:1947年[昭和22年]の法改正まで続いた制度のひとつで、嫡子に対して相続する権利を排すること)することを決意。跡継ぎを孫の渋沢敬三(笠松将)に頼むのでした。
そんななか、徳川慶喜(草彅剛)の伝記作りがいよいよ大詰めに。徳川慶喜のもとを訪れた渋沢栄一は、そこである言葉を伝えられます。
今週のトピック
最終回 青春はつづく(2021年12月26日放送)※15分拡大版
1909年(明治42年)に実業界を引退したあとも、渋沢栄一(吉沢亮)は、都市開発や教育・社会事業に力を注いでいました。そして念願の「徳川慶喜公伝」も完成させます。さらに渡米実業団を組織し、ワシントンの軍縮会議に合わせて再び渡米。貿易摩擦の解消や移民問題などの改善に尽力します。一方、渋沢栄一の跡を継ぐことになった孫の渋沢敬三(笠松将)は、銀行員となり、ロンドン支店に勤務。渡英する前に渋沢栄一のもとを訪れ、渋沢篤二(泉澤祐希)を許してほしいとお願いするのでした。
そんな折、1923年(大正12年)9月、関東大震災が発生。大被害を受けた日本のために、渋沢栄一は海外から寄付を呼びかけ、資金を集めます。その後も、大水害にあった中華民国を支援しようと、渋沢栄一は「中華民国水災同情会」の会長に就任。救援物資を集め、中国へ送ろうとします。しかし、直後に日本軍が満州の鉄道を爆破したことをきっかけに満州事変が勃発し、日本からの物資は拒否。渋沢栄一は日本の行く末を憂いながら、とうとう病に伏せてしまうのでした。
今週のトピック
知ればもっと楽しめる!青天を衝けの制作秘話
渋沢栄一の故郷・血洗島をオープンセットで表現!

ひこばえの木と論語の道
青天を衝けで、渋沢栄一が家族や幼馴染と青春時代を過ごす血洗島村は、群馬県安中市(あんなかし)にオープンセットが建てられました。広大なロケ地に建設された血洗島村の巨大セットは、まさに幕末に百姓が暮らしていた村そのもの。ロケに参加した俳優からも、驚きの声が上がったと言われています。
これほどまでに巨大なセットを建てることとなった理由は、渋沢家があった血洗島村と、のちの妻となる尾高千代や従兄の尾高淳忠らが暮らす尾高家の「下手計村」(しもてはかむら)との距離を表現するためです。
近所に住んでいた渋沢家と尾高家の実際の距離は、徒歩30分ほどだったと言われています。この距離感と当時の百姓の生活をリアルに表現するために、全長約1kmの広大なオープンセットが建設されたのです。
渋沢栄一は、尾高淳忠に学問を学ぶため、渋沢家と尾高家を行き来します。
渋沢栄一が論語を学んでいたことから、両家を結ぶこの道は「論語の道」と呼ばれるようになり、オープンセット内にも再現されています。
また、渋沢家と尾高家の間に位置する大木「ひこばえの木」も、若き渋沢栄一と幼馴染が集う象徴的な場所です。ひこばえの木にぴったりな大木があったことも、オープンセット建設地の決め手になったと言われています。
渋沢栄一が育った「中の家」こだわりのセット

桑畑
広大な村を建設したオープンセットと共に、青天を衝けの世界観を表現しているのが、中の家と呼ばれた渋沢家のセットです。
特に、当時の中の家を忠実に表現している注目ポイントのひとつが「桑の木」。製藍業と共に「養蚕業」(ようさんぎょう:主に製糸用の繭を生産する産業)を営む渋沢家には、蚕の餌である桑がたくさん栽培されていました。
この桑畑を作るために、オープンセットを担当する美術チームは、2020年(令和2年)1月から約3,000本もの桑を植えて撮影に向け準備を開始。地元農家の方々からも協力を得て、無事に渋沢家の周囲に広大な桑畑を作ることができたのです。

渋沢家(中の家)
また、スタジオに作られた、中の家母屋の内部セットには、養蚕業には欠かせない数万匹の蚕を育てる養蚕部屋も。養蚕部屋での撮影には、本物の蚕も登場しています。
さらに、渋沢栄一の父・渋沢市郎右衛門が藍染めを行う「土蔵」(どぞう:火災や盗難に備え、四面を土や漆喰で固めた倉庫)のセットにも注目です。青天を衝けのために、スタッフが独自に作った土蔵は、勤勉家で研究熱心な渋沢市郎右衛門を表現するための特別なセットだと言えます。藍染め研究を行う父の姿勢を見て、渋沢栄一の商売への道が開かれることとなるのです。
青天を衝けの鑑賞は、スタッフがこだわり抜いて作ったスタジオセットも、細部まで注目してみると、より楽しめるのではないでしょうか。